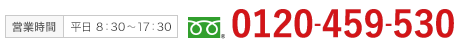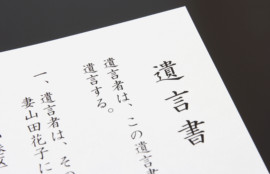Q.私は3年前に父から会社を引き継いだのですが、父は会社の株式をまだ保有しており、また父から会社への貸付金が多額に残っています。相続人は母、私、私の兄と妹の4人です。
そこで、少なくとも事業に関係する財産(株式・貸付金)は私が引き継ぎたいので、父に遺言書を書いてもらおうと思っています。
しかし、最近父の物忘れがひどく、認知症の心配があります。認知症だと遺言書が書けないと聞いたことがありますが、どうしたらよいでしょうか。
A.病院で判断能力の検査を受け、その結果が被保佐人・被補助人相当であれば、通常と同様の手続で遺言書を作成することができます。一方で被後見人相当と判断されれば、医師の立会など特別な手続が必要となります。
なお、前者の場合でも、遺言能力に疑義が生じることのないように、事前に医師の診断書に「本人の遺言能力に問題はない」と一文を入れてもらうことや、出来るだけシンプルな遺言内容にすること、付言事項として遺言者の想いを残しておくこと等により、トラブルとなる可能性を更に大きく減らすことができると考えます。
第1 前提となる法制度
1 後見・保佐・補助制度
民法では私的自治の原則が採られており、私人は、自己の自由な意思決定により自らの権利義務関係を形成することができるとされております。
もっとも、認知症等によって判断能力が不十分な方は、自らの意思で適切に財産の処分や管理をすることができませんので、このような方についてまで私的自治の原則を貫くことは適切ではありません。
そこで、民法では、判断能力が不十分な方を保護するために、後見・保佐・補助制度が設けられております。
すなわち、判断能力が不十分な方については、家庭裁判所の審判により、後見人・保佐人・補助人といった第三者が本人に代わって財産管理を行うこととされております。
第三者が財産管理を行うことにより、本人が自ら管理することによる財産散逸の危険を防止し、また、近親者が本人の財産を私的に流用する危険を防止することが可能となるわけです。
そして、民法は、本人の判断能力の程度に応じて、次のとおり後見・保佐・補助の3つの制度を定めております。
① 後見 ~本人の判断能力が全くない又はほぼない場合
判断能力が不十分な本人を「被後見人」、本人に代わって財産管理等を行う第三者を「後見人」と言います
② 保佐 ~本人の判断能力が著しく不十分な場合
判断能力が不十分な本人を「被保佐人」、本人に代わって財産管理等を行う第三者を「保佐人」と言います
③ 補助 ~本人の判断能力が不十分な場合
判断能力が不十分な本人を「被補助人」、本人に代わって財産管理等を行う第三者を「補助人」と言います
2 被後見人・被保佐人・被補助人の遺言作成
(1) 被後見人の遺言作成
前記1のとおり、被後見人には判断能力がほぼありません。
このため、被後見人は、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識するに足りる能力(遺言能力)を備えておらず、単独で遺言を作成することはできないとされております。
したがって、被後見人が有効な遺言を作成するためには、特別な手続が必要であり、被後見人が能力を一時回復している時に医師2人以上の立会のもとに作成しなければなりません(民法第973条)。
(2) 被保佐人・被補助人の遺言作成
他方、被保佐人・被補助人は、判断能力が不十分ではあるものの、遺言を作成することが可能であり、被後見人のような特別な手続は要求されておりません。
したがって、被保佐人・被補助人は、通常人と同様の手続によって遺言を作成することが可能であり、医師の立会も必要とされておりません。
もっとも、被保佐人・被補助人も、判断能力が(著しく)不十分な状態にあり、遺言能力がない状況下で遺言が作成された遺言は無効となります。
第2 本件への当てはめについて
1 判断能力の程度
判断能力の検査方法として、HDS-R(長谷川式簡易知能評価スケール)、MMSE(認知機能検査)の2つの方法があります。
家庭裁判所では、ひとつの基準として、
・HDS-Rの得点が10点以下の場合には「後見」、11点以上15点以下の場合には「保佐」に該当する
・MMSEの得点が14点以下の場合には「後見」、15点以上17点以下の場合には「保佐」に該当する
と運用されているようです。
本件において、父が訪問したX病院作成の診断書によりますと、父の診断結果は、HDS-Rの得点が15点、MMSEの得点が18点とされております。
したがって、家庭裁判所の上記基準によりますと、HDS-Rの得点は「保佐」相当(ただし最も軽い程度)、MMSEの得点は「補助」相当にあたります。
少なくとも、「保佐」ないし「補助」相当であり、「後見」にはあたらないと言えるかと思われます。
2 軽度の認知症の方の場合
前記第1の2に記載しましたとおり、被保佐人・被補助人は、通常人と同様の手続によって遺言を作成することが可能であり、医師の立会などの特別な手続は要求されておりません。すなわち、遺言者の判断能力が被保佐人や被補助人と同程度であれば、通常人と同様の手続で遺言を作成することが可能と言えます。
もっとも、被保佐人・被補助人であっても、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識するに足りる能力(遺言能力)が必要であり、これがないと判断される場合には遺言が無効となってしまいます。
この点において、遺言者の判断能力が被保佐人・被補助人相当であるとしても、他の相続人から、「遺言作成当時、被相続人には遺言能力がなく、そのような状況下で作成された遺言は無効である」と争われる危険が存在します。
特に、遺言の内容が特定の相続人にのみ財産を相続させる内容の場合には、遺言によって財産を相続することができない相続人が不満に感じ、紛争に発展する事例が数多くあります。
そこで、以上のような遺言の有効・無効の問題が発生する危険があるのであれば、次の①~③などのような方法により、遺言作成を慎重に進めるのが良いのではないかと思います。
➀ 再度医師の診断を受け、「本人の遺言能力に問題はない」「遺言の内容を理解し、その結果を弁識することができる状態である」などと記載された診断書を取得する。
HDS-RやMMSEで高い点数が記載された診断書でも、遺言者に遺言能力があったことを示す重要な証拠となりますが、それに加えて、医師から上記のような診断書も取得しておけば、更に安心度は高まると思われます。
➁ 遺言の内容を複雑にしないこと
判断能力が十分でない遺言者が自ら複雑な内容の遺言を考える、ということは想定し難いのではないかと思われます。
したがって、遺言の内容を複雑にすればするほど、他の相続人は「遺言は本当に被相続人の意思によって作成されたのだろうか」「他者の入れ知恵ではなかろうか」と考えるのではないかと思われます。
換言しますと、遺言の内容がシンプルであればあるほど、判断能力が十分でない遺言者であっても、自らそのような遺言を考えることが可能であったと言いやすいと思われます。
したがって、遺言の内容は複雑にすべきではないと思われます。
➂ 遺言者のお気持ちを付言事項にすること
遺言を作成する場合、末尾に「付言事項」として、なぜそのような遺言の内容にしたのか、その理由などを記載することがあります(例:長男は老後の身の回りの世話をしてくれたため、長男に多く配分することにした等)。
もし遺言者に何か遺言を作成する理由があるのであれば、それを「付言事項」として遺言の末尾に記載しておくと、遺言者の意思が明確に示されることになりますので、無効と判断されづらくなると思われます。
また、遺言者のお気持ちが遺言に記載されることになりますので、他の相続人の不満も出づらくなるのではないかと思われます。
いかがでしたでしょうか。
認知症が疑われる方の遺言書の法的有効性については慎重に判断されることをおすすめします。このような案件は弁護士案件となりますので、当センターが窓口となり、弁護士をご紹介させていただきます。
やはり、認知症になる前に可能な限り早めに相続対策を考え、行動に移すことが肝要です。